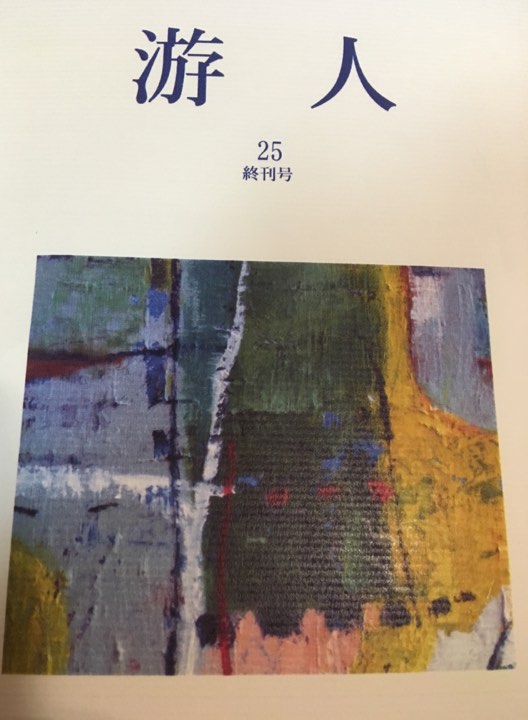■「主宰者のいない同人誌」、詩誌「游人」25号(終刊号)
番場早苗さんの「夜の岸で」、「ボー」という船の汽笛の音・・・「そうだ亡だ茫だ茫茫だ滂沱の雨だ涙だ人生だ」・・・幼い頃、聴いたことがあります。30年くらい前まで、毎夏、函館市戸井地区(旧戸井町)の父の育った家を訪れていました。早朝、窓から見える遠くの海に光る点が動く、あれが船だよ、烏賊釣り漁船のランプ。昆布漁師の古い家でした。ボートに乗って、大きなレンズで海中を覗き、ツブやウニ拾いを拾ってバケツへ。石の上にコンブを開いて干し、その上をタコが歩き、スミを吹きかけられました。生まれて初めてカレイを釣った。いつの間にか毎年行くのをやめてしまい、それ以来、何年も函館に行くこともなく、太陽の沈む水平線をじっと眺めたり、無数の生き物たちが揺れ動く海中を泳いだ経験も遠い昔となってしまいましたが、小学校中学年くらいまで経験できた「游」の感覚、水の中で光が揺れて計り知れないほど多くの生き物がお互いのために生きている、その中の一部になれた経験・・・「総目録」を拝見すると、ちょうど「游人」創刊の頃から函館へ行かなくなってしまったのだと恋しく思います。街のほうや北斗市にも親戚が住んでいて、潮の香り、坂の景色を思い出します。「ボー」は一瞬にして遠い場所へ連れて行ってくれる魔笛のよう。「闇にゆられて目を閉じれば/ああ 十七の夏だ/あのひとと会った/朝の海だ」(番場早苗さん「夜の岸で」)
河田節さんの「遠景」、「温もりのように/赦しのように/気高く/荘厳に/そんざいしていた」、消えてしまった幾重もの遠景に生かされている。「日はのぼり 日はしずみ」一つの終わりはきっと始まり。
木田澄子さんの「塩の市(しおのいち)」、《仄聞》という言葉から想起される人々の声が市の歴史を創り上げていくような壮大な幻想に囚われました。
長屋のり子さんの「死者たちの輪唱(カノン)が聴こえる」、引用されている「生きている者は死者たちにとり囲まれている」(ジョン・バージャー)・・・大学時代、恩師の高野斗志美先生に、「柴田の詩には死者たちの中で生きているというのが足りない」と指摘を受け、励まされたことを強烈に憶えております。戦争をくぐりぬけて、「存在の核に響く痛み」を抱え、死者たちの中で生きているという感覚を強く抱いていた高野先生に与えられた課題でした。死んでいった人たちが作った詩歌が時代を超えて繰り返し、あらゆる言語で歌い継がれる。「死者たちの輪唱(カノン)が湧きあがる。死んだ人たちは、こんなにも不死なのだと夢の中で私は熱く感嘆する。」(長屋のり子さん「死者たちの輪唱(カノン)が聴こえる」)
「游人」同人の皆様の御作品、エッセイ、フィナーレの総目録、海の街で星空を見上げる気持ちで拝読させて戴きました。
5月25日の豊平館ライブにて、僭越ながら、詩誌「游人」終刊に捧げる詩を朗読させて戴けましたら幸いです。